エナメル・THE ENAMEL 1
エナメルは、紀元前ギリシャやエジプトに始まって中国を経て日本に伝わり、多様な技法によって宝飾品に使われてきた永い歴史がある。
19世紀末アールヌヴォー時代には透明なエナメルがジュエリーにさかんに用いられ大流行期を現出した。
ロンドンの大英博物館やパリのプチ・パレ美術館には、エナメル彩色した金台の上に豪華な宝石が散りばめられたアンティーク・ジュエリーの逸品が数多く展示されている。宝飾プロなら必見の価値がある。
近年、エナメルという言葉は、宝飾品からはやや離れて存在し、ある種の塗料を含む多数の製品に加工されている。例えばイタリア革製品ハンドバッグや靴の表面にエナメル加工されている。また陶器の表面に光沢を出すのに使用されている。
宝飾製品に使われる高級エナメルは、これら一般エナメルと区別するために単にENAMELでなく、THE ENAMEL 又は AN ENAMELという。このように欧米のジュエリー業界では線引きして区別しているようだ。
エナメルの関連用語として、七宝焼、七宝町、リモージュ、クロワゾネ、釉薬(ゆうやく)などがあるが、これらはエナメル必須用語で宝飾業界人なら知らぬと恥をかくことになる。
エナメルは日本語で七宝焼と云われている。七宝焼は、土台に金、銀、銅などの金属を用い、その表面にガラス質の釉薬(表面に色を出すための薬)を盛って800度~850度の高温で焼き付ける工芸法で、この焼付けは7回以上行うので、宝を7回焼くから七宝焼といわれるようになったとある中国宝石商は説明する。
七宝焼の「七宝」とは、仏教の経典には極楽は七宝によって装飾されているという。
その七つの宝物とは一般に金・銀・るり・はり・メノウ・サンゴ・シャコである。但し、般若経ではシャコがなくコハクが入り、法華経では、はりとサンゴがなくコハクと真珠が加わっている、瑠璃はラピス・ラズリ、はりはガラスのことで、日本では仏教伝来以来珍宝として尊重されてきた。七宝焼は、七つの宝を散りばめたように美しいの意味から由来する。
この七宝焼で有名なのは国内では、愛知県海部郡七宝町で、ここには七宝焼アートヴィレッジ(電話:052-443-7588)があって七宝焼博物館がある。ちなみに国内には玉造の名の付いた所が全国各地にある。古くからヒスイ・メノウの工芸品産地にこの玉造の地名が多い。
リモージュ・Limogesはフランスの中部の都市リモージュで、16世紀に完成した良質のLimoges Enamelで、黒または灰色のバックに白のエナメルを塗り重ねたモノトーンの色変化が特徴的で、人物像などを上絵付けの形で焼き付けた作品をいう。可憐な少女や美しい婦人の細密画をリモージュ・エナメルで仕上げたブローチやペンダントなどの宝飾品にしたものが多い。髪の毛や肌の質感まで巧みに表現されジュエリーの逸品に仕上がっている。現在は伝統的なものから抜け出して明日の新作品をめざして多くの作家が活躍している。ほかに多彩なスイス・エナメルも有名だ。
クロワゾネ・CLOISONNE この用語クロワゾネは“仕切った場所”を意味するフランス語の“CLOISON”から来ている。数ある七宝焼技法の一つ有線七宝で、金属地金の表面に細い金属線か針金でデザインを形づくりハンダ付けしてつくったセルにエナメルをつめる。各セルはそれぞれ特別につくったものを詰めて火に入れる。粉状にエナメルは融着すると収縮してセルを完全に埋めないので、再びエナメルを詰めて火に入れて焼く、この骨の折れる細密手作業工程はセルがエナメルで充填されるまで何回も繰り返す。この焼付け工程、炉に入れて焼くのは、7回繰り返すといわれる。中国の珠玉商の中には、この困難な手間のかかる焼付け工程が7回もあるので七宝焼というと説明するものもいる。最近は高級腕時計の文字盤にクロワゾネ加工されたものが出ている。(クロワゾンネとも云う)。
「楽しいジュエリーセールス」
著者 早川 武俊

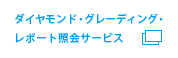
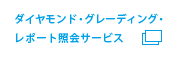
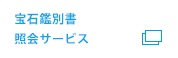









 の市場の何倍もある義烏市の福田市場はまさに中国一の大きさがゆえ1日2日ですべてを回りきることが出来ません。私は杭州に宿泊し、毎朝定期直行バスで毎日往復いたしましたが歩きやすい靴と服装で行かれることをお勧めいたします。アクセサリー市場は、本当にびっくりするほどの安さです。工賃は、あってないようなものです。しかしほとんどの店舗が、卸売りのため最小ロットを設けていますので、1個では購入できません。ある程度数を想定していかれると話が早いと思います。本当に日本に入ってきているメイドインチャイナの商品の大部分はこの市場で買えるのではと思ってしまいます。値段も思っている10分の1ぐらいで。是非読者の皆さんも中国一の卸売市場で新商品を見つけて販売にお役立て下さい。もっと詳しい情報やご質問がありましたら下記メールをいただきましたらわかる範囲でお答えさせていただきます。
の市場の何倍もある義烏市の福田市場はまさに中国一の大きさがゆえ1日2日ですべてを回りきることが出来ません。私は杭州に宿泊し、毎朝定期直行バスで毎日往復いたしましたが歩きやすい靴と服装で行かれることをお勧めいたします。アクセサリー市場は、本当にびっくりするほどの安さです。工賃は、あってないようなものです。しかしほとんどの店舗が、卸売りのため最小ロットを設けていますので、1個では購入できません。ある程度数を想定していかれると話が早いと思います。本当に日本に入ってきているメイドインチャイナの商品の大部分はこの市場で買えるのではと思ってしまいます。値段も思っている10分の1ぐらいで。是非読者の皆さんも中国一の卸売市場で新商品を見つけて販売にお役立て下さい。もっと詳しい情報やご質問がありましたら下記メールをいただきましたらわかる範囲でお答えさせていただきます。
























