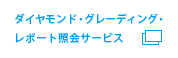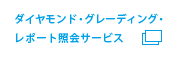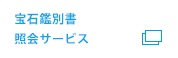エメラルドは、深い緑色が魅力的な最も美しい宝石の一つです。内包物が比較的多い石ではありますが、その緑色の深さが十分であれば内包物の存在で評価を落とすというよりもその色調により高い評価が与えられている宝石です。
エメラルドの名前は「緑色の宝石」を意味するラテン語“smaragdos”やギリシャ語“smaragdus”に由来し、それらがフランス語の“esmeraude”となり、現在の“emerald”に変化したと言われています。この素晴らしい宝石には多くの物語がありますが、その殆どは南米大陸での話です。南米では今でもエメラルドが大量に産出されており、古代のインカ族やアステカ族もこの石を神聖な石として崇拝していました。しかしながら、おそらく知られている限り最も古いエメラルド産地の記録は紅海の近辺からのものでしょう。西暦紀元前3000年から1500年の間にエジプトのファラオによってエメラルドはすでに珍重されており、クレオパトラも愛用していたと伝えられています。
鉱物としてのエメラルドは、7.5~8の硬度を持つベリリウム・アルミニウム・ケイ酸塩鉱物で、アクワマリンやモルガナイトと同じベリル鉱物に属します。純粋なベリルは無色ですが、結晶が形成される過程でほんのわずかなクロムやバナジウムが加わることによりすばらしい緑色を呈するわけです。
このようなクロムやバナジウム成分とベリリウムやアルミニウム成分は地球化学的な性質が違う元素で、それぞれが異なる火成活動と関連しています。性質の異なるそれぞれの火成活動が同一の地域で重なって起こり、はじめてこれらの成分が出会い、美しいエメラルドを作り上げます。
多くのエメラルドが今日オイルまたは天然の樹脂で習慣的に加工されています。これはエメラルド結晶をカットした際に表面上に露出したキャビティからの液体の流失により空気が入り込み、その結果 石の内部へと続くキャビティを白く目立たせ、エメラルドの色そのものを低下させる、それをカバーするための加工です。オイルを含浸したエメラルドはキャビティ中のオイルが再び流失してしまう恐れもあるため、石の取り扱いには十分な注意が必要です。特に、エメラルドは超音波で洗ってはいけませんし、洗剤に浸すことも避けるべきです。
産地
エメラルドは南極以外の6大陸から産出があります。その中でも南米大陸は最も重要で、特にコロンビアは最も産出量が多く、そして最も素晴らしい品質のものが産出されます。だからと言って「産地」が自動的に品質を保証すると考えることは間違いです。良質のエメラルドがザンビア、ブラジル、ジンバブエ、マダガスカル、パキスタン、インド、アフガニスタン、あるいはロシアのような他の国でも産出されます。特にザンビア、ブラジル、そしてジンバブエは良質のエメラルドであると国際的な評判を得ています。ザンビアのエメラルドは、透明度が良くて美しい濃いエメラルドです。その色はコロンビアの石よりもっと一般的に濃く、青味がかっています。ブラジルでは、イタビラ鉱山やサリニンア鉱山が有名ですが、ブラジルのものは緑色がやや黒味を帯びているのが特徴です。ジンバブエの有名なサンダワナ鉱山のものは、一般に小さいが、鮮やかな濃い緑色でしばしば黄色がかっています。
1. 南米
コロンビア
コロンビアのエメラルドはスペイン人がやって来るずっと以前から先住のインディオの手で採掘されていました。スペインの征服者がコロンビアに侵入し、彼らは大量のエメラルドをインディオから奪い、更にソモンドッコ(碧の石の神)と呼ばれるエメラルド鉱山の在りかをも聞き出したのです。1537年、ここにスペイン人が鉱山を開き、これが現在のチボール鉱山につながっていきます。またムゾー鉱山は、1564年、ムゾーの町でスペイン人が馬のひづめの下に光る緑の石の断片を見つけたことがきっかけとなり今日のムゾー鉱山が生まれたと云われています。
コロンビアのエメラルドは、青色を含まないその良質なすばらしい緑色によって他の産地のものと区別されます。ムゾー鉱山は、コロンビア最大の鉱山であるとともに、最高級のエメラルドを産出するという定評があります。緑色が濃いうえに柔らかい味わいがあります。コスケス鉱山のものは淡い緑色に特徴があります。チボール鉱山のものはムゾー鉱山のものと比較すると内包物は少なく透明度が高いです。緑色にやや青色味がかっているのも特徴です。他にガチャラ、ピナピスタ鉱山などが以前は良質なものを産出していたが、最近では産出されていません。
◆母岩:黒色、雲母、パイライト、方解石
◆内包物:三相内包物、黒色頁岩(コロンビアだけの特徴的内包物)、パイライト

ギザギザした輪郭の液体キャビティ中に
気泡と結晶を含む三相内包物

黒色の粒状で含まれる頁岩の内包物

トラピッチェ エメラルド
◆吸収スペクトル:クロム/バナジウム関連の吸収バンド。トラピッチェは鉄関連の吸収バンドを見せる。
◆屈折率:低め(通常光1.570~1.584、異常光1.564~1.578)
ブラジル
<バイア州>
○カルナイーバ鉱区

バイア産エメラルド
1965年、バイア州のほぼ中央部を北から南に150kmに伸びるジャコビナ山地一帯に豊富なエメラルド鉱床が発見されました。たちまちエメラルド・ラッシュとなり、国中から無数のガリンペイロが押し寄せて一大鉱山町が出現しました。しかし、近年ではエメラルドの生産は大幅に減少しています。
○サリニンハ鉱区
1963年、バイア州サン・フランシスコ川流域にてサリニンハ鉱山が発見されました。
片麻岩と滑石片岩にレンズ状に貫入したペグマタイト脈にエメラルドが生成した鉱脈です。明るい黄色味を帯びた半透明の小さな結晶は良く粒が揃っていますが、結局わずかな量のみを産出したのみで鉱脈が枯渇しました。
サリニンハのエメラルドにはクロムが少なく、バナジウムによる着色であったためエメラルドではなくグリーンベリルと呼ぶべきだという論争を巻き起こしました。
<ゴイアス州>
○サンタ・テレジーニャ鉱区
1981年、ブラジルの首都ブラジリアから北西に230km程のゴイアス州のサンタ・テレジーニャにエメラルド鉱山が発見されました。
結晶は平均して1cm未満と小さいのですが、1立方メートル当たり11カラットと高品位です。 また他のゴイアスのエメラルドと比べるとクリーンな透明な結晶が多いと言われます。
サンタ・テレジーニャ鉱山はキャッツ・アイやスターといった効果を示すエメラルドの産出が多いことが特徴です。キャッツ・アイ・エメラルドは他にも報告がありますが、スター・エメラルドは大変稀で、サンタ・テレジーニャの特産です。

マッチ箱を少し潰したような結晶の
カルサイト内包物
◆母岩:炭酸塩、滑石、金雲母の片岩
◆内包物:ピコタイト、カルサイト、滑石、パイライト、磁硫鉄鉱、黄銅鉱など
◆吸収スペクトル:クロム/バナジウム関連の吸収バンドと鉄関連の吸収バンドを見せる。
◆屈折率:低め(通常光1.588~1.600、異常光1.580~1.590)
<ミナス・ジェライス州>
ブラジルの宝石や金属資源の宝庫として知られているミナス・ジェライス州では1979年に州都ベロオリゾンテから東に100km程のベルモントでエメラルドが発見されました。

イタビラ産エメラルド
○ベルモント鉱山
◆最も機械化が進んでいる同州では現在一番の鉱山
◆品質:小粒であるが高品質
◆母岩:雲母片岩で結晶を回収し易い。
○イタビラ鉱山
◆古い鉱山で現在でも原始的な方法で採集している。
◆品質:色は暗いものが多いが、中には上質のものもある。
◆母岩:雲母片岩に炭酸塩岩、滑石が含まれているため非常に硬く、結晶が回収し難い。
(つづく)
【GYOHO 質屋業報 2006年10月号 より転載】