江森 健太郎

写真1 MexiFire(左)と PeruBlu(右)
タイのRMC Gems Thai社から新しいタイプの合成オパールが市場に出されています(写真1)。これらはこれまでの合成オパールに見られたような遊色効果は無い、所謂コモンオパールで、オレンジとブルーの2種類がそれぞれMexiFireとPeruBluという商品名で販売されています。
今回、これら2種類の合成オパールを検査する機会に恵まれ、全国宝石学協会の小林泰介さんと阿依アヒマディさんと共同で研究した結果を平成20年度の宝石学会(日本)福岡総会で報告しました。
宝石学的特性
MexiFire、PeruBluの外観および屈折・比重・蛍光は以下の通りです。
MexiFire
外 観:オレンジ色を呈し、遊色効果は示さない。キズのないメキシコ産天然ファイア・オパールに酷似する。透明度が高く、ガラス光沢をしている。
屈折率:1.35
比 重:1.57(静水法)
蛍 光:長波紫外線下で微青白色、短波紫外線下で微黄緑濁
PeruBlu
外 観:エレクトリックブルーと称されるような彩度の極めて高いブルーで遊色効果はない。
屈折率:1.39
比 重:1.75(静水法)
蛍 光:長波・短波紫外線下で共に不活性
拡大検査
拡大観察では、密度が高く散在した微小インクルージョンによるクラウドと気泡が石全体にみられました(写真2・左)。また、天然オパールでは観察されない微細な波状成長構造が認められます(写真2・右)。
今回観察した合成オパールは遊色効果を持たないコモンオパールであり、京セラやギルソン製の合成オパールに見られるようなリザードスキンは認められませんでした。

写真2 拡大検査で観察される小さな気泡(左)と波状成長模様(右)
分光検査
近赤外領域のスペクトルでは、MexiFireには天然ファイア・オパールには見られない約2260nmの位置に強い吸収があり(図1・左)、PeruBluでは天然ブルー・オパールとの差は見出せませんでした(図1・右)。しかし、MexiFire、PeruBluともに通常の合成オパールには見られない水や水酸基に伴う吸収が認められ、極めて天然オパールに類似することがわかりました。

図1 近赤外領域のスペクトル
(左:MexiFireと天然ファイア・オパール、右:PeruBluと天然ブルー・オパール)
FT-IR(赤外分光分析)では、MexiFireの透過スペクトル及び反射スペクトルは一般的なオパールに酷似します。しかし、透過スペクトル中の吸収ピークを細かく観察すると、天然ファイア・オパールは弱い吸収ピークが約4500cm-1に出現するのに対し、MexiFireは約4420cm-1に強い吸収と約4500cm-1に弱い吸収があることがわかります(図2)。

図2 MexiFireと天然ファイア・オパールの赤外領域スペクトル
成分分析
この2種類のオパールについて、蛍光X線装置による成分分析を行ったところ、MexiFireは主成分である珪素の他に微量の鉄が、PeruBluは珪素の他に微量の銅が検出されました。その他の特徴のある成分はどちらのオパールにも見出せませんでした(図3)。

図3 蛍光X線分析チャート(左:MexiFire、右:PeruBlu)
また、LA-ICP-MS(レーザー・アブレーション誘導結合プラズマ質量分析)による微量分析を行ったところ、着色元素である鉄と銅以外では両色のオパールに、ホウ素、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、スカンジウム、チタン、クロム、マンガン、ニッケル、亜鉛、ストロンチウム、ロジウム、すず、鉛が検出されました。天然ファイア・オパール、天然ブルー・オパールにはこのタイプの合成オパールには検出されない、ベリリウム、バナジウム、ガリウム、ストロンチウム、ウランなどの微量元素があり、天然と合成でマグネシウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、亜鉛の元素の含有量に差異があることがわかりました。
走査型電子顕微鏡による観察

写真3 PeruBluの後方散乱電子像

写真4 PeruBluのFE-SEMを用いた
二次電子像(x100,000)
PeruBlu1点を2つに切断し、走査型電子顕微鏡(HITACHI-S3000H)を用いて観察しました(写真3)。この写真は後方散乱電子像で観察したものです。後方散乱電子像は、組成の違いをコントラストで現す像です。このPeruBluの後方散乱電子像はコントラストが均一であることから、このオパールの組成は均一であることがわかります。
また、この断面をフッ酸とメタノールの混合溶液でエッチングした後、電界放射型の走査型電子顕微鏡(FE-SEM)の二次電子像で観察しました(写真4・10万倍)。この写真より、このオパールが小さな粒状のもので構成されていることがわかります。この粒はオパールを形成する珪酸球で、スケールより、この珪酸球は10nm程度の粒径であることがわかります。通常、遊色効果を持つオパールは200nm程度の粒径を持ち、規則的に充填されています。遊色効果はこの粒径と規則性によって起こるものですが、このPeruBluは粒径が10nm程度と非常に小さいことが遊色効果を持たない理由になります。
X線粉末回折による実験
このPeruBluの珪酸球の構造を調べるために、(銅をターゲットにした)X線粉末回折実験を行いました。得られたチャートを下に示します(図4)。2θが21.8゚あたりのピークがブロードになっています。また、31.3゚、35.5゚、48.1゚に強いピークが観測されます。21.8゚あたりのピークがブロードであることは、このオパールはOPAL-A、つまりこのオパールを構成する珪酸球は非晶質であることがわかります。しかし、非晶質なオパールの場合、今回観測された31.3゚、35.5゚、48.1゚のあたりのピークは出ません。これらのピークはOPAL-C、OPAL-CT(クリストバライト、トリディマイト等結晶質な珪酸球で構成されたオパール)では観測されるものですが、OPAL-C、OPAL-CTの場合、21.8゚のピークは通常シャープになります。
なぜ、このようなピーク形状になってくるのか、まだわかりません。このオパールを形成する珪酸球はほとんどが非晶質ですが一部クリストバライト、トリディマイトが含まれている可能性があります。

図4 PeruBluのX線粉末回折チャート
溶液による実験
PeruBluを過酸化水素水に漬けたところ、反応を起こしました。PeruBluは元々エレクトリックブルーと称されるような彩度の強い青色を呈するのですが、過酸化水素水につけることによって、深緑色に変化しました。この変化は非常に早く、ものの数分で変色してしまいます。しかし、この深緑色になってしまったPeruBluは、時間を置くとある程度の青色を取り戻していきます(写真5)。しかし、完全に元の色に戻るわけではありません。

図5 PeruBluを過酸化水素水につけた際の色変化
このPeruBluの過酸化水素水による色の変化のメカニズムは、硫酸銅水溶液に過酸化水素水を加えた場合に起こる現象と同じだと思われます。
まず、硫酸銅水溶液に過酸化水素水 (H2O2) を加えると、酸素を発生しつつ、色が深緑色にかわっていきます。この際、Cu2++ H2O2→ [Cu(H2O)]2++ (1/2)O2↑という反応がおこります。硫酸銅溶液中の銅はCu2+として存在し青色ですが、[Cu(H2O)]2+ は深緑色です。
この [Cu(H2O)]2+ は不安定な存在で、容易に分解し、[Cu(H2O)]2+→ Cu2++ H2O と元の青い Cu2+ に戻ります。
今回のPeruBluでも同様の反応が起こっていると推測され、これはこのPeruBluに含まれる銅は珪酸球中の不純物として存在しているのではなく、オパールに含まれる水の中にイオンとして存在し、青色を発色しているものと推測されます。
まとめ
RMC Gems Thai社が新しく製造販売している2種類のオパールMexiFire、PeruBluの2点についての特性は上記にまとめた通りですが、天然のファイア・オパール、ブルー・オパールと比重、屈折、拡大検査などで容易に区別可能です。また赤外、近赤外の領域の分光チャートでも天然、合成に差異があり、鑑別の際の手助けになります。
今回、PeruBluの構造について調べた結果、珪酸球の粒径は10nm程で、非晶質なものがほとんどですが、中にはクリストバライト化しているものも含んでいる可能性があります。なお、このPeruBluが遊色効果を持たない理由は珪酸球の粒径が非常に小さいからだと考えられます。
また、PeruBluの発色原因がオパール中の水の中に溶けている銅イオンであるため、このPeruBluは銅イオンの存在する溶液中で、コロイド状のシリカを沈殿させ、生成したものであると推測されます。
今回MexiFireについては構造等調べていませんが、おそらく同様のものであると推測されます。
今回の研究では、京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室鉱物学研究室の北村雅夫教授、下林典正助教授、三宅亮助教授の協力で、走査型電子顕微鏡「S-3000H(HITACHI)」とX線粉末回折装置を使用させていただき、研究上重要な助言をいただきました。それぞれ感謝を申し上げます。

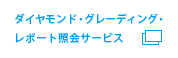
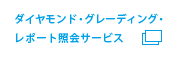
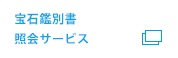


 (ホンハム、Hung Hom)にはたくさんの宝飾関連の企業が入居するビルがあります。ダイヤモンドサイトホルダーからジュエリー工場、パッケージ会社までこの周りだけでいろいろな会社と商談することができ、期待した工場がきっと見つかると思います。ここは香港では古くから工業地区として栄え、区域内には黄埔ドッグという造船所がありました。現在はその名残として黄埔地区内に黄埔号という船の形をしたモニュメントがあり、日系スーパージャスコや商店が入居しており、観光スポットの一つとなっています。また近年は海岸沿いやMTR東鉄線紅
(ホンハム、Hung Hom)にはたくさんの宝飾関連の企業が入居するビルがあります。ダイヤモンドサイトホルダーからジュエリー工場、パッケージ会社までこの周りだけでいろいろな会社と商談することができ、期待した工場がきっと見つかると思います。ここは香港では古くから工業地区として栄え、区域内には黄埔ドッグという造船所がありました。現在はその名残として黄埔地区内に黄埔号という船の形をしたモニュメントがあり、日系スーパージャスコや商店が入居しており、観光スポットの一つとなっています。また近年は海岸沿いやMTR東鉄線紅 、東莞、広州、上海、北京など中国へ向かう列車の紅
、東莞、広州、上海、北京など中国へ向かう列車の紅













![図5 PL[a]](img/01-zu05.jpg)
![図6 PL[b]](img/01-zu06.jpg)
![図7 PL[c]](img/01-zu07.jpg)









 市編
市編





