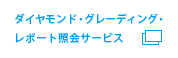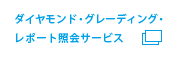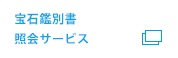Gemmy 152 号 「平成21年宝石学会(日本)「最近遭遇するいわゆるレアストーンの鑑別について(その2)」」
間中裕二・尾方朋子
さて、前号ではターフェアイトとマスグラバイトについて、その鑑別法・特徴を紹介しましたが、今回はポルダーバータイトとオルミアイト、グリーンマイクロライト、チカロバイトについて紹介します。
ポルダーバータイト(Poldervaartite)とオルミアイト(Olmiite)
写真3は、左のラウンドカット石が2003年ツーソンミネラルショーにおいてポルダーバータイトとして入手したもので、右のエメラルドカット石は最近オルミアイトとして鑑別結果を出したものです。色調もよく似ています。写真4は、オルミアイトの写真と鑑別データで、以前であればMn(マンガン)を多く含むために屈折率と比重が高いポルダーバータイトという結果を出していました。なお、それぞれの名称は、アメリカのコロンビア大学岩石学教授Arie Poldervaart(1918~1964)とイタリアの鉱物学者Filippo Olmiに因みます。

写真3:ポルダーバータイトとオルミアイト

写真4:オルミアイト
両者の比較
組成式を見ればわかるようにポルダーバータイトのCa(カルシウム)の一つがMnによって置換されたものがオルミアイトで、屈折率は端成分の値が表示されているため一見重なっていないようですが、実際には一つのCaとMnが置き換わるため自由に中間の値をとります(表3)。この両者を区別するにはCaとMnが置換する部分のMnが半分以上あればオルミアイトということになり、全体的なモル比で考えるとCa・Mnの中でMnが25%以上あればよいことになります。前号の冒頭でも記述しましたが、オルミアイトは2006年にIMA(国際鉱物学連合)で新しい鉱物種として登録されています。

表3:特徴比較
EDS
エメラルドカット石を測定してみると、CaとMnのモルでみた比率はMnが40%であり、オルミアイトとなります(表4)。また、2003年にポルダーバータイトとして入手したサンプルも現在ではオルミアイトに分類されます。

表4:オルミアイト組成
グリーン マイクロライト(Microlite)
マイクロライト自体、鑑別に持ち込まれることは稀で、さらに一般的には黄色や褐色の色調を示すのに対し、今回遭遇したマイクロライトはかなり鮮やかで濃い緑色を呈していました(写真5)。マイクロライトの名称は、通常小さな結晶(多くは集合体)として産出されることに由来します。

写真5:グリーン マイクロライト
EDS
マイクロライトは、大分類としてパイロクロール グループに属し、さらにマイクロライト サブグループに属していて、Ta(タンタル)がNb(ニオブ)より多いということが特徴の一つです。表5に示される通り、当該石は元素的なデータからもマイクロライトであることが分かります。また、インターネット上で鉱物のデータを共有・参照を目的としたRRUFFTMで緑色を示すマイクロライトについて調べてみると、写真と共にフルオナトロマイクロライト(Fluornatromicrolite)としての記載があります。

表5:マイクロライト組成
チカロバイト(Chkalovite)
チカロバイトは、透明無色で屈折率が1.54-1.55・比重が2.66とクォーツに近く、さらにインクルージョンも写真に示すようにクォーツにありがちな二相包有物もあり、石自体が小さかったり、マウントされているなど十分な情報が得られない場合、間違える可能性があるため注意が必要な宝石種です。記載では蛍光が強いと記述されていますが、今回鑑別した石は顕著な蛍光を示さなかったことと、二軸性の確認が容易ではなかったことも合わせて報告しておきます(写真6)。名称はロシアのValerii Pavlovich Chkalovに由来します。チカロフは1930年代に、はじめてノンストップでモスクワから北極点経由でアメリカまで飛行し、当時の長距離飛行記録を樹立した人物です。チカロフ自身は1938年、34歳の若さで飛行機事故により亡くなってしまいましたが、翌39年にチカロバイトとして鉱物に名を残したという逸話がある石です。
さて、鑑別に有効なのは、赤外分光です。中赤外のデータにも相違があり、遠赤外側のデータ(図7)が得られれば間違うことはありません。

写真6:チカロバイト

図7:FT-IR(遠)赤外
まとめ
☆ ターフェアイトとマスグラバイトの識別には、ラマン分光だけでなく、
赤外分光も有効、PLも指針となる
☆ ポルダーバータイトはオルミアイトの可能性大
☆ マイクロライトは黄色、褐色だけでなく濃緑色のものも存在
☆ チカロバイトはクォーツとの特性類似に注意