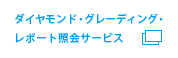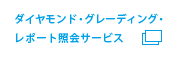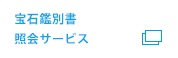Gemmy 138 号 「平成19年宝石学会「最近分析した石についての報告」」
本年6月に開催されました平成19年度の宝石学会(日本)にて当中央宝石研究所から発表致しました研究成果2件についてご紹介致します。今回は藤田所員が発表しました『最近分析した石についての報告』です。
「最近分析した石についての報告」 藤田 直也
『サンセットクォーツ』

写真1 サンセットクォーツ
2006年7月にブラジルのミナスジェライス州で、サンセットクォーツ(写真1)と呼ばれる新種の宝石が発見されました。色は透明なオレンジ色で、夕日のような色をしています。
屈折率や比重、偏光性は一般のクォーツの特性と一致し、蛍光性は弱く見られる程度です。拡大検査では、褐色の細い包有物(写真2)があり、水で浸液した状態で内部を観察すると、サンプル自体はほとんど無色で外観の色は褐色の包有物が影響していることがわかりました(写真3)。

写真2 褐色の細い包有物

写真3 浸液した状態
紫外-可視分光光度計で分析したところ、545nmに弱い吸収があり、390nmを中心としたブロードな吸収のほか、253nmに吸収がみられました(グラフ1)。本体が無色のクォーツであることを考えると、これらの吸収は褐色の包有物の影響と推測されます。また、フーリエ変換型赤外分光分析装置(FT-IR)を用いて分析したところ、3635cm-1に吸収がみられ、この吸収はサンセットクォーツ特有の吸収(グラフ2)であると思われます。

グラフ1 紫外-可視分光光度計のデータ

グラフ2 FT-IRのデータ

写真4 表面が充填されている
蛍光X線元素分析装置での分析では、主成分の珪素のほかに微量の鉄が検出されました。これも褐色の包有物に起因するものと思われます。
褐色の細い包有物が表面にでている(写真4)箇所は充填されており、顕微ラマン分光分析装置を用いてその箇所を分析したところ、エポキシ樹脂のデータとほぼ一致しました。
『ロシアンアマゾナイト』と『チャイニーズアマゾナイト』

写真5 ロシアンアマゾナイト

写真6 チャイニーズアマゾナイト
ロシアンアマゾナイトと呼ばれる石の屈折率や比重はアマゾナイトと一致し、色はやや緑色の濃い石から青緑色の石までありました(写真5)。
蛍光X線元素分析装置を用いて分析をしたところ、微量の鉛とルビジウムが検出されました。一般的なアマゾナイトと同様に鉛の量は色相が緑色に寄っている石の方がより多い傾向にあり、ロシアンアマゾナイトはやや緑色の濃いアマゾナイトであることがわかりました。
チャイニーズアマゾナイトと呼ばれている薄青色から青緑色までの石は、屈折率や比重、偏光性の反応は多結晶質のクォーツと一致します(写真6)。

写真7 青く細かい包有物
内部を拡大検査したところ、青く細かい包有物(写真7)が多数入っており、表面のくぼみにあった結晶(写真8)を顕微ラマン分光にて分析したところ、粘土鉱物のデータとほぼ一致しました。また別のサンプルでは、先ほどの包有物とは異なる青い色素(写真9)が表面のくぼみに見られましたが、この色素からはワックスが検出されました。
次に蛍光X線元素分析装置を用いて分析したところ、90%以上の珪素と数%のアルミニウムが石から検出されました。この検出されたアルミニウムは青い包有物に起因しており、この包有物の正体も粘土鉱物だと思われます。
以上の結果より、チャイニーズアマゾナイトは多結晶質のクォーツで、包有物は粘土鉱物であると考えています。表面のくぼみに色素がついている石は、これらの石に人為的な着色処理が施されることを示唆しています。

写真8 くぼみの中の結晶

写真9 くぼみに入った青い色素
『ブルーサファイアカラーのキュービックジルコニア』

写真10 キュービックジルコニア
最近、ブルーサファイアによく似た色相をしたキュービックジルコニアが鑑別に持ち込まれました(写真10)。
表面の光沢はサファイアよりギラギラした印象を与えますが、色はブルーサファイアによく似ており、はじめに指輪を手にした時に予想していた重量よりもはるかに重いので驚きました。キュービックジルコニアはブルーサファイアと比べて比重がとても重いため、石が大きくなればなるほど重さにその差が出てきます。
紫外-可視分光光度計で当該石を分析すると、グラフ3 のとおり一般的なブルーサファイアの色光分布(赤)とキュービックジルコニアの色光分布(黒)には似た傾向が見られますが、キュービックジルコニアには鋭いピークが数多く見られます。蛍光X線元素分析装置を用いて分析をしたところ、これはネオジムとエルビウムの影響であることがわかりました。
その他、このキュービックジルコニアは通常のよりもイットリウムが多く、ジルコニウムの量も少ないことが判明しました。

グラフ3 紫外-可視分光光度計のデータ